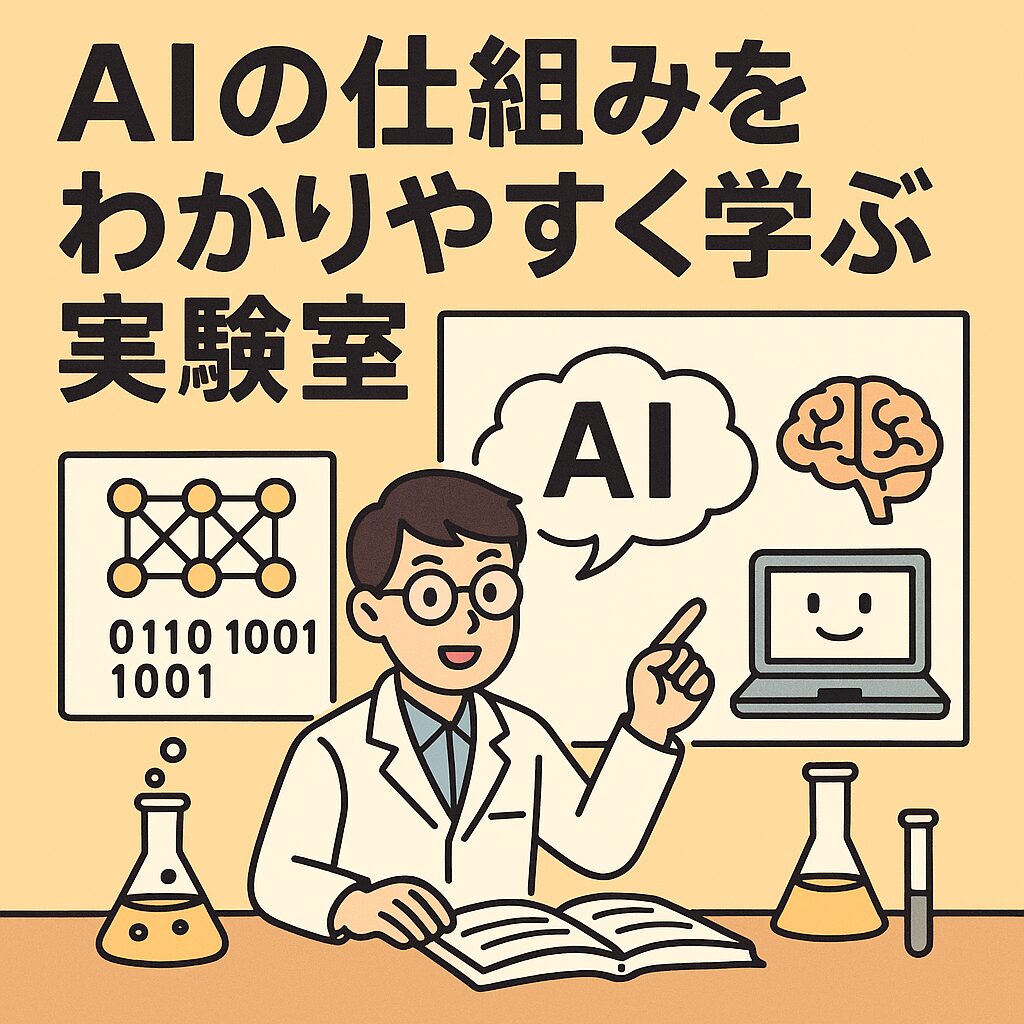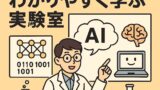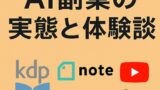AI画像生成といえば、Stable Diffusionという名前を耳にしたことがある人は多いでしょう。
無料で使えるのに高性能、しかも自分のパソコンでも動かせる――この特徴によって、Stable Diffusionは一気に世界中に広まりました。
しかし、その裏側には「潜在拡散モデル」という技術と、「オープンソースとして公開されたこと」による大きな文化的変化があります。
本記事ではStable Diffusionの仕組みを理論寄りに解説しつつ、派生モデル(LoRA・DreamBooth)の実用的な側面も厚めに扱います。
第1回でAIと機械学習の基礎、第2回で拡散モデルを理解した読者に向けて、今回は具体的な生成AIの代表例としてStable Diffusionを徹底的に掘り下げます。
Stable Diffusionとは?誕生と普及の背景
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- Stability AIと研究者コミュニティの協力
- オープンソース化の意義
- MidjourneyやDALL·Eとの違い
Stable Diffusionは「誰でも無料で使える」点が注目されがちですが、その背景を知ると普及の理由がより鮮明になります。
誕生の背景と開発思想
Stable Diffusionは2022年に公開されました。
開発元はStability AIですが、実際には多くの研究者やコミュニティが関与しています。
目指したのは「研究者や個人開発者が自由に使える生成AIモデルを作ること」。
この開かれた思想が、その後の爆発的普及を後押ししました。
なぜオープンソース化されたのか
当時、DALL·EやMidjourneyといった商用モデルはクローズドであり、利用者はあくまで「サービスを使う立場」に限定されていました。
一方、Stable Diffusionはモデルそのものをオープンソースで公開。
誰でもダウンロードして利用でき、改良や派生モデルの公開も自由に行える仕組みでした。
これが「AIは研究者や大企業のもの」というイメージを一気に変えました。
Midjourney・DALL·Eとの違い
Midjourneyは芸術的で高品質な画像を生み出しますが、利用はDiscord限定で生成物も公開が前提です。
DALL·Eは自然な文章理解に優れていますが、商用利用には制限がかかります。
対照的にStable Diffusionは「自由度」と「カスタマイズ性」で優位に立ちました。
Stable Diffusionを支える「潜在拡散モデル」の仕組み
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 潜在空間で処理するメリット
- ピクセル空間との違い
- ノイズ除去プロセスの流れ
Stable Diffusionのブレークスルーは「潜在拡散モデル(Latent Diffusion Model)」の採用にあります。
潜在空間とは何か?
従来の拡散モデルは、ピクセルごとにノイズを処理していました。
これは高品質な画像を得られる反面、計算コストが莫大でした。
潜在拡散モデルでは「潜在空間」という圧縮された特徴表現の領域で処理します。
要するに、画像を小さな要素に変換して効率的に扱う方法です。
画像を圧縮して扱う仕組み
Stable Diffusionはまず画像を「潜在表現」にエンコードします。
この表現は元画像の情報を凝縮しており、少ない計算量で操作が可能です。
その後、拡散モデルが潜在空間でノイズを除去し、最後にデコーダで元の解像度に戻します。
これにより、個人PCでも実用的な速度で生成が可能になったのです。
ノイズから画像を復元する流れ
完全なノイズを入力し、数十〜百数十ステップをかけて潜在表現を復元。
最終的に画像デコーダで高解像度の画像として出力します。
この流れは第2回で解説した拡散モデルの基本と同じですが、「潜在空間」を活用することで効率化されています。
学習データとテキスト理解の進化
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 学習データセット(LAION 5b)
- CLIPとOpenCLIP
- T5エンコーダ
Stable Diffusionの強みは、学習データとテキスト理解の進化にも支えられています。
LAION 5bとデータセットの課題
Stable DiffusionはLAION 5bという大規模データセットを利用しました。
これはインターネットから集められた画像とテキストのペアです。
膨大なデータ量によって多様な表現を学習できた一方、著作権や倫理の課題も指摘されています。
CLIPによるテキストと画像の結びつき
CLIPは「テキストと画像を同じ空間にマッピングする技術」です。
これにより「犬の写真」という言葉が画像とリンクし、自然な生成が可能になりました。
T5エンコーダで長文プロンプトに対応
Stable Diffusion 3ではT5-v1.1 XXLといった大型言語モデルが導入されました。
これにより、長く複雑なプロンプトでも忠実に再現できるようになっています。
バージョンごとの進化と改良
Stable Diffusionは複数の世代を経て進化してきました。
SD1.xの衝撃
SD1.4や1.5は、個人PCで現実的に実行できる初めての拡散モデルでした。
「大企業専用の技術」から「誰でも使える技術」に変わった瞬間です。
SD2.xとSDXL
SD2.xでは解像度が向上し、SDXLではフォトリアル表現が飛躍的に改善されました。
より多様で自然な画像が生成可能になり、ユーザー体験も大きく変化しました。
SD3の最新技術
Stable Diffusion 3は2024年に登場しました。
複数のテキストエンコーダを組み合わせ、Rectified Flow Samplingによって生成速度も改善。
最新世代として、さらに実用性が増しています。
派生モデルと拡張機能(LoRA・DreamBooth)
Stable Diffusionが文化的に大きな影響を与えたのは、この「派生モデル文化」の誕生にあります。
特にLoRAとDreamBoothは、ユーザーが自分専用の生成モデルを作ることを可能にしました。
LoRA(Low-Rank Adaptation)の仕組みと活用例
LoRAは既存の大規模モデルに対して「少量のデータで効率的に学習を追加する技術」です。
数十枚の画像でキャラクターの特徴や特定の画風を学習させられます。
たとえばアニメキャラクター風のLoRAを読み込めば、誰でもそのスタイルで生成が可能になります。
公開サイト(Civitaiなど)では無数のLoRAが共有されており、利用者は自分好みのスタイルを自由に追加できます。
DreamBoothの仕組みと活用例
DreamBoothは「特定の対象をモデルに取り込む」ための技術です。
たとえば自分の顔写真を数十枚学習させれば、その人物を生成画像の中に自然に登場させることができます。
商品写真を学習させれば、広告素材を効率的に作れるなど、マーケティング用途にも広がっています。
ただし肖像権や著作権のリスクがあるため、実用時には注意が必要です。
コミュニティと派生文化
LoRAやDreamBoothを通じて作られた派生モデルは、Hugging FaceやCivitaiといったコミュニティで公開されています。
「二次創作モデル」「写真風LoRA」など多様なモデルが登場し、経済圏も形成されつつあります。
Stable Diffusionが「単なるツール」を超えて「文化のプラットフォーム」となった理由がここにあります。

【Amazon スマイルSALE初売り開催中! 1/7まで】欲しいものは、いますぐチェック👇
今年の運試しはAmazonの福袋で!!
欲しいアイテムは、今のうちにAmazonでまとめ買い!!
実際にStable Diffusionを試す方法(補足)
理論理解のためには実際に触れてみることも有効です。
Webサービスで試す
Hugging Face SpacesやMage.spaceなど、ブラウザだけで試せる環境があります。
ローカル導入
AUTOMATIC1111 WebUIはもっとも利用者が多い環境です。
さらにComfyUIはノードベースで処理を組み立てられる高度なツールです。
商用利用とライセンス
ライセンスの基本
Stable DiffusionはRAIL-Mライセンスで公開されています。
基本的に商用利用は可能ですが、悪用を禁じる規約が含まれています。
著作権・倫理的課題
学習データに既存の作品が含まれている可能性があり、利用者には責任が求められます。
Adobe Fireflyとの比較
Adobe Fireflyはライセンス済みデータで学習しており、生成物に対してIP保証があります。
安全性を重視するならFirefly系が適しているケースもあります。
Stable Diffusionを学ぶ推奨図書
- 『ゼロから作るDeep Learning』斎藤康毅
¥3,740 (2025/09/28 14:23時点 | Amazon調べ) ポチップ
ポチップ
- 『深層学習』Ian Goodfellow 他
- 『Stable Diffusion スタートガイド』白井暁彦/AICUmedia編集部
¥2,640 (2025/09/30 20:05時点 | Amazon調べ) ポチップ
ポチップ
まとめと次回予告
今回はStable Diffusionの仕組みと進化を理論寄りに解説し、LoRAやDreamBoothといった派生モデルの文化まで紹介しました。
Stable Diffusionが「誰でもAIを使える時代」を切り開いた理由は、潜在拡散モデルの効率化と、オープンソース公開による派生文化にあります。
次回は「DALL·E 2/3と再キャプション技術」を取り上げ、商用モデルがどのように精度を高めているのかを解説します。
※この記事は2025年10月5日時点の情報に基づいています。最新情報は公式サイト等をご確認ください。
公式発表に加え、観測報道ベースの情報も含みますので、今後の動向を確認しながらご活用ください。
📖 著者「ちゃっとまる」のKDP作品一覧
AI活用・ビジネススキル・小説まで――
幅広いテーマで執筆した書籍を
Amazon Kindleで公開中です。
👉 Kindle Unlimitedなら 読み放題。
定期的に期間限定 無料キャンペーン も開催中!
ぜひこの機会にチェックしてください。