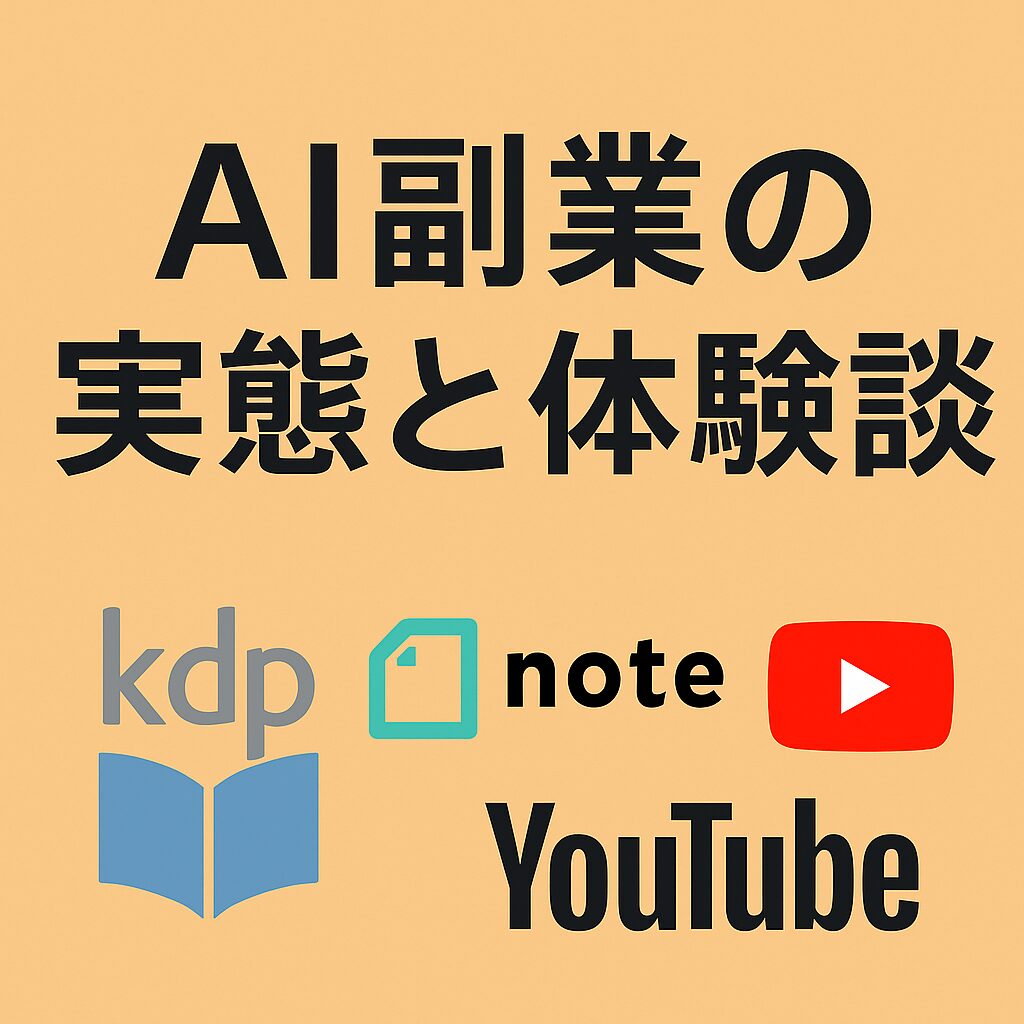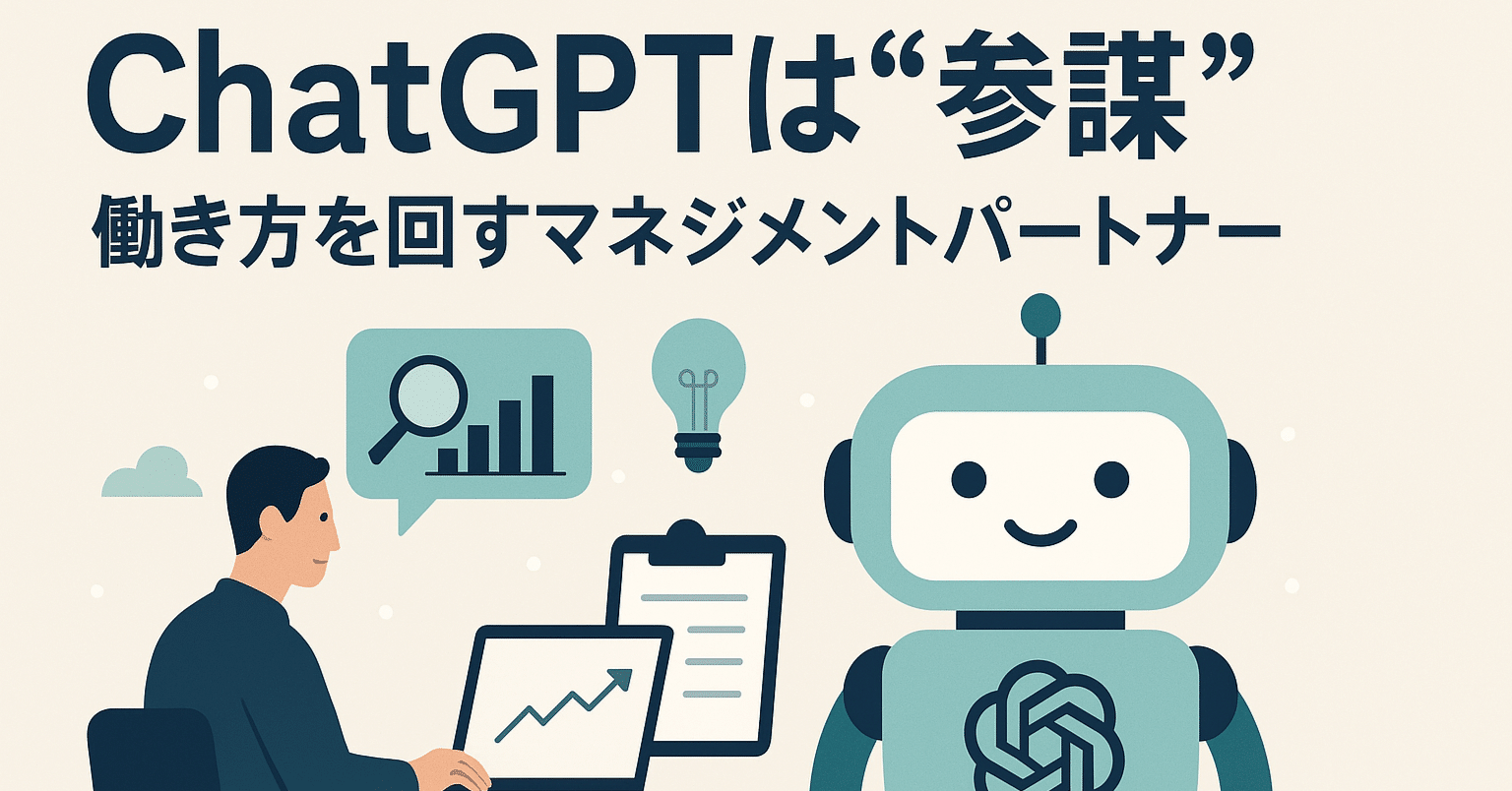AI副業を始めたいけれど、実際の現場感や収益の手触りがわからず不安ではありませんか?
本記事では、私が今週取り組んだKDP出版の絵本制作、note記事執筆、YouTube運営のリアルな実態と気づきを共有します。
うまくいったことも失敗も含め、次の一手に生かせる具体策をまとめました。
KDP出版で学んだ市場調査の重要性
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- ChatGPT・nano banaan・Canvaを使った絵本制作体験
- 電子書籍市場の実態と紙書籍の強さ
- 副業初心者こそ市場調査が必須な理由
結論として、制作の前に市場の現実を押さえるだけで方向性の精度が一気に高まります。
AIツールの活用で調査の手間は劇的に下がり、仮説検証のスピードが副業の成否を左右します。
ChatGPT・nano banaan・Canvaを使った絵本制作体験
ブログ企画の一環でKDPでの絵本制作に挑戦しました。
物語設計はChatGPTで骨子を作り、リライトとトーン調整を重ねて世界観を固めました。
ビジュアルはnano banaanで下絵の素案を生成し、Canvaでレイアウトと装丁を整えました。
この組み合わせにより、少人数でも短期間で“見られる”作品に到達できる手応えを得ました。
制作速度が上がる一方で、企画の方向を誤ると労力が無駄になるリスクも強く感じました。
電子書籍市場の実態と紙書籍の強さ
制作の過程で国内の電子書籍のシェアを調査しました。
結果は予想外で、電子書籍全体のシェアは約30〜40%という把握になりました。
内訳を見ると、電子の伸びは主にコミックが牽引し、実用書や児童書は依然として紙が優勢です。
とくに絵本は紙の比率が高く、9割程度が紙という印象でした。
私は電子派だったため、電子のみで勝負できるという思い込みが崩れ、ペーパーバック化に舵を切りました。
副業初心者こそ市場調査が必須な理由
新しい副業ほど「自分の好み」ではなく「市場の現実」を起点にするほうが安全です。
ChatGPTに調査観点や仮説の棚卸しを依頼すれば、検索より速く漏れなく着地点を作れます。
需要の強い媒体や価格帯、訴求キーワードを先に確かめれば、制作の手戻りは激減します。
作り方の詳細は別記事に譲りますが、まず調査、次に試作、最後に量産という順番が結果的に最短でした。
AIで調査の参入障壁が下がった今こそ、はじめの一歩で差がつきます。
note記事執筆で感じた「テーマ選び」と反応の大切さ
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 特集テーマに沿った記事執筆の効果
- ChatGPTを「参謀」と位置づけた理由
- 記事の最後に導線を設ける戦略
結論として、プラットフォームの特集に乗ると初速が上がり反応が集まりやすくなります。
記事の最後にCTAを設置して、ブログやYouTube、KDPへの導線を用意すると全体の成果が伸びます。
特集テーマに沿った記事執筆の効果
noteで「#働き方を変えるツール」特集が始まりました。
私のテーマと親和性が高かったため、すぐに一本目の記事を投入しました。
特集は露出機会が増えるため、フォローやスキの初期反応が得やすいと感じました。
検索エンジンの評価待ちを必要としない点が、ブログと並走させる価値です。
初速の反応が可視化されると、次のネタ出しと検証に勢いが出ます。
ChatGPTを「参謀」と位置づけた理由
執筆テーマは「ChatGPTは参謀」という切り口にしました。
数多のツールを横断的に紹介するよりも、実務の汎用性が際立つ中核に絞ったほうが伝わります。
構成案の生成、仮説のチェック、見出しのAB案、語尾の単調さ回避など参謀的タスクに最適でした。
結果として、記事品質の底上げと作業時間の圧縮を同時に実現できました。
読後の納得感が高いのか、保存やスキの反応が早かった点も印象的でした。
記事の最後に導線を設ける戦略
noteは単発で終わらせず、出口に複線を引くほうが効果的です。
記事末尾にブログ、YouTube、KDPのCTAを配置し、興味の深さに応じて回遊できるように設計しました。
導線は三択程度に抑えると迷いが減り、クリック率が安定します。
LP的に整えすぎるより、体験ベースの自然な誘導のほうが相性が良いと感じました。
特集の波に合わせて、関連投稿を短い間隔で重ねる施策も検討中です。
❓ ChatGPTを使いこなせていますか?
新しいAIツールを試しているが、どれも使いこなせていない。
プロンプト集を購入したが、結局思った通りの結果を得ることができない。
👉 実はChatGPTを使いこなせば、多くの課題が解決可能です。
ChatGPTを使いこなすポイントをNoteに纏めました。
このnoteは成長型なので、今後✅ ChatGPTと一緒に作るPythonアプリ開発入門、✅ Difyノーコード開発なども追加予定です。
YouTube運営で直面した更新頻度とツール選びの壁
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 更新頻度が収益化に直結するYouTubeの現実
- Runway導入で感じたメリット・デメリット
- AI美女Liliaのライブ映像実験と反響
結論として、YouTubeは継続が正義であり、制作負荷をツールでどう下げるかが勝負です。
コンテンツ軸を複線化し、短尺と長尺を織り交ぜて本数を確保する運用に切り替えました。
更新頻度が収益化に直結するYouTubeの現実
一週間以上、更新が止まり登録者が一名減りました。
テキスト中心の作業と比べると動画は制作時間の固まりが必要で後回しになりがちです。
視聴者は日常的にYouTubeを開くため、空白期間が長いと存在感が薄れます。
反省として、無理なく回せる“最低限の更新ライン”を先に設計すべきでした。
短尺の在庫を持ち、長尺にリソースが割けない週はショートでつなぐ体制を作ります。
Runway導入で感じたメリット・デメリット
本数を増やすためにRunwayを有料導入しました。
年間五割引で月7ドルというコスト感は、継続運用の心理的ハードルを下げます。
一方でアバター機能のクレジット消費は重く、ショート3〜4本が実質上限でした。
高機能のアバター系は概してコスト高で、費用対効果の見極めが必要です。
アバター前提の構成を減らし、映像生成と編集のワークフロー最適化に比重を移します。
AI美女Liliaのライブ映像実験と反響
アバター依存を下げるため、短いライブ風映像を複数作って2分の動画に再編集しました。
SUNOの楽曲を上に載せ、ショートとして配信する形に切り分けました。
初回のライブ映像は配信6時間で400回前後の閲覧を獲得し、小さな手応えを感じています。
コンテンツ軸は3本立てにし、投資格言の解説、作業用BGMの長尺、ライブ映像ショートを回します。
これにより、制作負荷のばらつきを吸収しつつ更新を止めない仕組みを整えます。
👇こちらが作成したライブ映像🎥 気に入ったらチャンネル登録もお願いします!!
今週のAI副業から得た気づきと今後の方針
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 思い込みを避けるための市場調査
- 特集への便乗で初速を確保
- YouTubeは更新ラインの設計が鍵
結論として、AI副業は「小さく早く作り、数字で見極め、続けられる形に最適化する」が王道です。
来週はペーパーバック化の進捗共有、noteの連投実験、ショートの週次最低3本体制を目標にします。

【Amazon スマイルSALE初売り開催中! 1/7まで】欲しいものは、いますぐチェック👇
今年の運試しはAmazonの福袋で!!
欲しいアイテムは、今のうちにAmazonでまとめ買い!!
付録|来週に向けた実務チェックリスト
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- KDP:ペーパーバックの体裁チェックと表紙差し替え
- note:特集タグに合わせた二本目の企画案
- YouTube:ショート三本のテンプレ化と台本プリセット
結論として、テンプレ化と在庫化が継続の壁を最も低くします。
以下の最低限タスクを回し、改善サイクルを週次で刻みます。
KDPチェックリスト
ペーパーバックの内製テンプレを作り、余白とノドの安全マージンを固定します。
表紙は背幅自動計算のスプレッドシートを作成し、次回以降の手戻りを無くします。
カテゴリとキーワードは3案を先にAB検証し、無料キャンペーンとの連動を図ります。
noteチェックリスト
特集タグの近接テーマを列挙し、シリーズとして期待される見出しを先に提示します。
記事末のCTAは三択に整理し、クリック計測で翌週の配置を最適化します。
OG画像はシリーズ共通の枠に差し替え、視認性と連続性を高めます。
YouTubeチェックリスト
ショート用台本を150文字前後で雛形化し、録音と編集のバッチ処理にします。
Runwayの使用は映像生成に寄せ、アバターは月内のクレジット上限を先に割り振ります。
週次の最低3本と、月次の長尺1本をKPIに設定し、欠番時のバックアッププランを用意します。